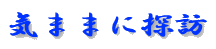 「海から一番遠く星に一番近い町」 (2)
「海から一番遠く星に一番近い町」 (2)<<<Back Next>>>
 ■龍岡城五稜郭(たつおかじょうごりょうかく)
■龍岡城五稜郭(たつおかじょうごりょうかく)龍岡藩主松平乗謨(のりかた)が本拠を佐久に移すために造った龍岡城は、函館とともにわが国に2つしかない星形城郭
JR小海線臼田駅の裏の住宅街の一角に、西洋式の築城技術を採用した風変わりな龍岡(たつおか)城跡があり、わが国に2つしかない五稜郭の1つで、そして我が国最後のお城でもある。
現在敷地は田口小学校が使用しています。


 西の陵堡(りょうほ) 大手門付近 大手門跡、現在小学校の校門
西の陵堡(りょうほ) 大手門付近 大手門跡、現在小学校の校門
 ■御台所
■御台所明治4年(1871年)、明治政府が全国の城郭の取り壊しを命じたことから、龍岡城五稜郭もそのほとんどが取り壊されてしまいました。しかしながら、御殿の一部である御台所(おだいどころ)だけは、学校としての使用申請が認められたため、現在でも当時を知る唯一の遺構として残されています。
 ■星形の優れた城郭
■星形の優れた城郭 函館と龍岡城は、なぜ星形の城郭にしたのか。
日本の近世城郭は姫路城が、江戸初期に完成を見て、その後は幕府によって新規の築城も禁止され、ほとんど進化していません。
幕末に欧米諸国の黒船がやってきて、遅ればせながら、日本も重火器に対応した防御施設を構築する必要性に迫られ、そこで手っ取り早く導入されたのがフランス流の築城術です。
五稜郭は、実戦上、優れた城で、各陵堡(りょうほ)に回転自由な大砲を設置することにより敵からの死角をなくすことができるという、守るに易く攻めるに難しい構造をもっていました。
 ■松平乗謨(まつだいらのりかた)
■松平乗謨(まつだいらのりかた)藩主松平乗謨は、洋学を積極的に取り入れたほか崩壊間近の幕閣にあって、老中格・陸軍総裁の要職にありました。
また、明治に入ると、松平乗謨は大給恒(おおぎゅう ゆずる)と改名して佐野常民(さのつねたみ)とともに博愛社(現在の赤十字社)の設立に尽力しています。