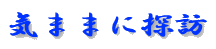 「本堂再建300周年の善光寺」 (5)
「本堂再建300周年の善光寺」 (5)<<<Back Next>>>
■善光寺に伝わる裏話 1

 ☆経車
☆経車回転することにより経典を読んだと同じご利益があると言われています
◆経堂
1759年の建立
お堂の中に経車がありお経が納められており回転出来るようになっており1回転でお経を読んだと同じ功徳があるとされている普段は回す事が出来ないが御開帳期間中と彼岸は出来る。
 ◆親鸞聖人 松を捧げている像
◆親鸞聖人 松を捧げている像浄土真宗の開祖親鸞聖人は越後国府(新潟県上越市)に流罪に成り善光寺参拝を許され100日間滞在しその時、毎日仏前に松をお供えしたそうです。
 それ以来数百年親鸞のお花松と称し本堂の花瓶に飾られています。
それ以来数百年親鸞のお花松と称し本堂の花瓶に飾られています。 ◆爪彫りの如来像
◆爪彫りの如来像このお堂の中に一枚の板に彫られた如来像が安置されている。 親鸞上人が善光寺詣でに訪れた時に一枚の板に爪で如来様を書いたものとされています。


 ◆「傷の柱」と「ねじれた向拝柱」
◆「傷の柱」と「ねじれた向拝柱」右の傷のついた柱は1847年の善光寺大地震のおり上の軒鐘がはずれて柱に当たった跡とされています。
左の「ねじれ柱」は大地震の時にずれたと言う説があったが現在では柱が狂うのを見込み建築されたからと言われています。 向拝柱が108本使われている。
 ◆堂前の護法石(ごほうせき)
◆堂前の護法石(ごほうせき)本堂正面の燈篭脇に大きな石があるが本堂を守る意味で護法石と名付けられていて、本堂を建立したときの道具を埋め石を立てたもので道具塚とも言われています。
☆護法石に関するお話
昔、念願であった善光寺詣に近所誘い合い旅に出たが信州に入るには厳しい峠越えをしてこなければならず善光寺を目前に力尽きて仲間の一人が亡くなってしまい「折角ここまで来て残念な事だ 俺たちが極楽浄土出来る様にお参りして置くから」と旅を続け善光寺に着てみたら亡くなった筈の仲間が石の上に腰掛けて一行の来るのを待っていたと言う話があり、それから善光寺に行くと亡くなった友人に会えると言伝えられています。