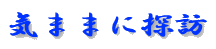 「本堂再建300周年の善光寺」 (4)
「本堂再建300周年の善光寺」 (4)<<<Back Next>>>
■本堂再建300周年
平成19年4月14日国宝の本堂が再建され今年で3百年を迎えたことを祝う記念法事が大勢の参拝客の集まる中行われました。
善光寺本堂は建立以来、11回の火災に会い現在の本堂は1707年(宝永四年)松代藩の協力で再建され江戸中期の寺院建築を伝える貴重な財産として1953年(昭和二八年)国宝に指定されています。
本堂の欄干には300周年に因んで300個の提灯が本日より11月まで飾られ祝う事になりそほか記念行事が行われます。




 ◆秘仏の本尊
◆秘仏の本尊 善光寺の本尊は「三国伝来の日本最古の御仏」と言われ秘仏で誰も見たことが無いとされている。
本堂の裏に回ると開かずの扉がありその中にご本尊が安置されています。
善光寺のご本尊は秘仏であるため分身の前立本尊が七年に一度本堂に安置され一般公開されますこれを御開帳と言い期間中の境内に45Cm角の長さ10Mの大きな回向柱が立てられ柱と前立本尊右手に「善の綱」で結ばれており回向柱に触れることにより阿弥陀様と縁が結ばれるとされています。
1っ箇所開いていない扉が「開かずの扉」ここに、ご本尊が安置されている



本堂に遷座の前立本尊の厨子 回向柱 法要 (資料:03年に行われたご開帳)
 ◆善光寺本堂
◆善光寺本堂 善光寺は参詣者の無宗教の寺で知られており、善光寺の住職は善光寺山内天台宗の本坊大勧進の住職(貫主と言う)と善光寺山内浄土宗の本坊大本願の住職(上人と言う)の2の宗派の寺が善光寺の住職を務めている。 正面が24m奥行きが54m,「T」字型の撞木造り(しゅもくづくり)。
入口から外陣、内陣、内々陣に分かれており、Tの字の─の部分が本尊を祀る金堂(内々陣)で、│の部分が礼堂(内陣、外陣)です。 昔は参拝客が内陣に寝泊りが出来たと言う。