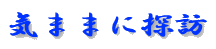 「本堂再建300周年の善光寺」 (3)
「本堂再建300周年の善光寺」 (3)<<<Back Next>>>
 ■「三門」
■「三門」 1750年建立
山門中央に掲げられている善光寺の額は1801年作
通称「鳩字の額」と言われ五羽の鳩と一匹の牛が隠されています。
現在、平成の大改修に入っていて平成21年まで見ることが出来ません
善光寺では正式には「三門」を使っていて仏教での三の空間を潜り抜けるところから「三門」と書くそうです。

 左:工事中の仮の「鳩字の額」
左:工事中の仮の「鳩字の額」右:工事に入る前の山門と1801年作「鳩字の額」
 ■善光寺は2寺院の住職が務める
■善光寺は2寺院の住職が務める◆大勧進
善光寺山内天台宗の本坊
住職は「貫主」(かんす)と、呼ばれ善光寺の住職を兼ねていて、毎朝、本堂で行われる「お朝事」の行き帰りに参詣者はお数珠の頂戴を受けられる。善光寺の朝の風物詩となっています



大勧進護摩堂 右:大勧進小松貫主
 ◆お数珠頂戴(おじゅずちょうだい)
◆お数珠頂戴(おじゅずちょうだい)早朝、本堂前の参道で半腰になり頭を垂れ、合掌してお数珠頂戴を待っています。
参拝客は宿坊に泊まり、早朝参列しますが、昔は本堂にお籠りして参列したそのために撞木(しゅもく)造りと言い内陣を広く取り独特な構造の建築となっています。
お朝事は毎日行われ,季節により時間が変わります。
駅前から「お朝事」に間に合う一番電車接続のバスも出ています。
 ◆大本願
◆大本願 善光寺山内浄土宗の本坊
善光寺創建時、皇極天皇のお杖代として大臣蘇我馬子の姫君が善光寺御守護職になったことからそれ以来、住職は代々公家から尼公上人が勤めています。
 中央:大本願鷹司上人
中央:大本願鷹司上人
工事現場から古瓦が出土し初期の本堂はこの位置に有ったのではと話題となっています:左端の工事用重機が見える位置

 ◆濡れ仏と六地蔵
◆濡れ仏と六地蔵☆濡れ仏
1722年建立。山門の手前右側に鎮座 江戸の大火の折、処刑された八百屋お七の冥福を祈り出家した吉三郎が建てたと言う伝説。
☆六地蔵
六地蔵は仏教の地獄、餓鬼畜生、阿修羅、人、天の六の苦しみを救うとされ建立1759年に造られたが現在のものは戦後に再興された。